
こんにちは!データサイエンティストの青木和也(https://twitter.com/kaizen_oni)です!
今回の記事では、他家の1人が副露で攻めてきている状況における押し引き判断について、「新科学する麻雀」を参考にしながら、自分なりの見解を付与して紹介していきたいと思います。
他家立直時についてのベタオリ/押し判断は新科学する麻雀のおかげで確率の高い打ち方ができていると自負していますが、他家副露時の対応についてはまだまだな部分があるので、今回記事としてまとめてみました。
科学麻雀を打たれている方々の刺激になれば幸いです!
1軒副露仕掛け時の前提の確認
これから議論を進めていく際の1軒副露の前提について、新科学する麻雀では以下のように定めています。
とつげき東北「新科学する麻雀」(ホビージャパン/2021) P167
- 手配内の現物(アンパイ)の枚数は2枚
- 副露者は赤ドラ含みの仕掛けではない
- 副露テンパイ時は、自分は1副露とする
1軒副露仕掛け時に1シャンテンで攻めるべきでない場面
新科学する麻雀に記載されている押し引き判断表によれば、ベタオリの方が優位性の高い場面はおおまかに以下のような状況です
メンゼン1シャンテン時
- 親が3副露しており、自身がカンチャン+リャンカンで立直1飜しかないときの無筋
- 親が3副露しており、自身がカンチャン両面の1飜またはカンチャンリャンカンの立直2〜3飜または立直七対子で9巡目以降に無筋456
- 親が2副露しており、自身がカンチャン+リャンカンで立直1飜しかないときの9巡目以降無筋456
- 子が3副露しており、自身がカンチャン+リャンカンで立直1飜しかないときの無筋456
副露1シャンテン時
- 親が3副露しており、自身がカンチャン+リャンカンで1飜しかない時のスジ、無筋全て(つまりアンパイ以外切るなということ)
- 親が3副露しており、自身がカンチャン+リャンカンで2飜しかない時の無筋456
つまり、以下4つの軸を考慮する必要があるということです。
- 相手の得点の期待値(親か子か)
- 自身の得点の期待値(何飜か)
- 自身のテンパイ確率(受け入れは)
- ロンされる確率(打牌)
まずは、上記のベタオリ判断から総合して分かることをまとめていきましょう。

ベタオリ判断から分かること
ベタオリ判断から分かることは以下3つと考えられます。
- 2〜3飜しかない場合は親2副露の時点で撤退も考えよう
- 2シャンテン以上あって打点上昇が見込めない場合は子2副露の時点で諦めてしまうのもあり
- 副露愚形1~2飜になってしまうような攻め方はしない
上記について順を追って解説していきます。
親の2副露以上でカンチャン+リャンカンで立ち向かう場合は満貫以上の手であれば安心だが、2〜3飜しかない場合は親2副露の時点で撤退も考えよう
これはつまり、以下のような状況を指します
- 相手打点期待値高(親につき)
- 相手テンパイ確率高
- 自分打点期待値中
- 自分テンパイ確率低
相手の打点やテンパイまでの近さについては、麻雀は情報が非対称なゲームなので分かりませんが、とはいえ、相手の打点期待値とテンパイ確率が高そう、要は振り込み期待値が高い状況で、自身の打点とテンパイという目に見える情報が振込期待値と釣り合わない場合は撤退しましょう、ということです。
一方で、自身の手が愚形2シャンテンだとしても満貫ぐらいのインパクトがあれば、親2副露ぐらいに対しては相手のテンパイ確率も少し低いので、振込期待値とアガリ期待値がトントンなのではないか、と考察しています。
逆に、親3副露の場合はリーチを食らっているものと同等に考えて、満貫に仕上がる手だとしてもそこに辿り着くまでに2枚必要(つまり2シャンテン)なのだとしたら、その牌はすでに他家が持っており永遠に1シャンテンにすら辿りつかない可能性があるので、筋を切りつつ撤退に向かってもいいかもしれません。

逆に子が2副露の場合は、カンチャン+リャンカン1飜という苦しい状況以外は攻められるが、2シャンテン以上あって打点上昇が見込めない場合は2副露の時点で諦めてしまうのもあり
親の2副露下と比べて、子の2副露は打点が33%低いことからもう少し強気で攻めることが可能になっています。
しかし、子の3副露で無筋を切らないという条件は1飜の愚形1シャンテンの状況下で言えることであって、愚形2シャンテンの場合には子の2副露時点でどのような振る舞いをするのか考える必要があります。
例えば、自身の手が1飜愚形2シャンテンの9巡目で子から2副露が入っている状況では、自身の得点に対する期待値から言っても、相手の得点に対する期待から言っても、降りてもいいと言えるかもしれません。
このような1シャンテン、テンパイ以外の判断については新科学する麻雀については記載はありませんが、2シャンテン以上は1シャンテンの前の状態と考えることによって、1シャンテン時の押し引き判断から逆算して推測することとなります。
一方で、1シャンテン押し引き判断を2シャンテン押し引き判断に転用する場合に、ベタオリすべき巡目をどこに設定するかについては、その人がどのような麻雀性向があるのかがある程度反映されてもいい部分と言えるかもしれません。

副露愚形1~2飜になってしまうような攻め方はせず、せめて愚形解消鳴きをしてテンパイする形を目指そう
親3副露時で、自身が1飜の愚形待ち確定の際にはアンパイ以外切るな、という非常に厳しい条件になっています。
これは副露をしている以上一発やツモ、裏などによる打点上昇が見込めないため、リーチ比較した時に期待値が低いため、攻める価値も相対的に低いためです。
なおかつ、副露をして手牌が狭まっているためアンパイを手にする確率が下がり、振込確率も上がっています。
このことから学べる教訓は、「どのように先を見越して鳴くべきか」ということです。
つまり、鳴くべき状況に対する以下のような考察ができます。
- 最後に良形が残るように鳴くべし
- 打点が高くなる見込みがある場合に鳴くべし
- 自身のアガリ確率が低い(テンパイが遠いなど)の状況ではよほどの打点がない限り鳴かない方が半荘終了時の得点期待値は高くなる
つまり、ベタオリ条件の逆を言えば、3飜以上あるのであれば無筋456を切り飛ばしても副露済みでも有利だし、リャンメンリャンメンであれば1飜でも無筋456を切り飛ばしてもいいのです。
最終形・打点の良さというのがいかに押し引きの場面で重要となってくるのかがお分かりいただけるかと思います。

まとめ
今回の記事では、新科学する麻雀の「1軒副露仕掛け時下、1シャンテンから攻めるべきか」というテーマから、1シャンテンに至るまでの状況でどのように判断すべきかについて、考察を進めていきました。
考察を深めていく中で、新科学する麻雀に書かれているに押し引き判断表の根本にあるのは、当然ながら相手の得点期待値と自分の得点期待値のバランス、そして得点期待値の構成要素は打点とアガリ率であることが分かりました。
そして、押し引き判断をせざるを得ないような相手2副露、3副露の状態で自身が勝負できるような手であるために、そこに至るまでにどのような手を作るかが重要であることもわかりました。
皆さんも新科学する麻雀の考えを取り入れながらも、書籍に載っていない部分については自身の判断を織り交ぜながら、麻雀における全ての判断の精度を高めていっていただけると幸いです!


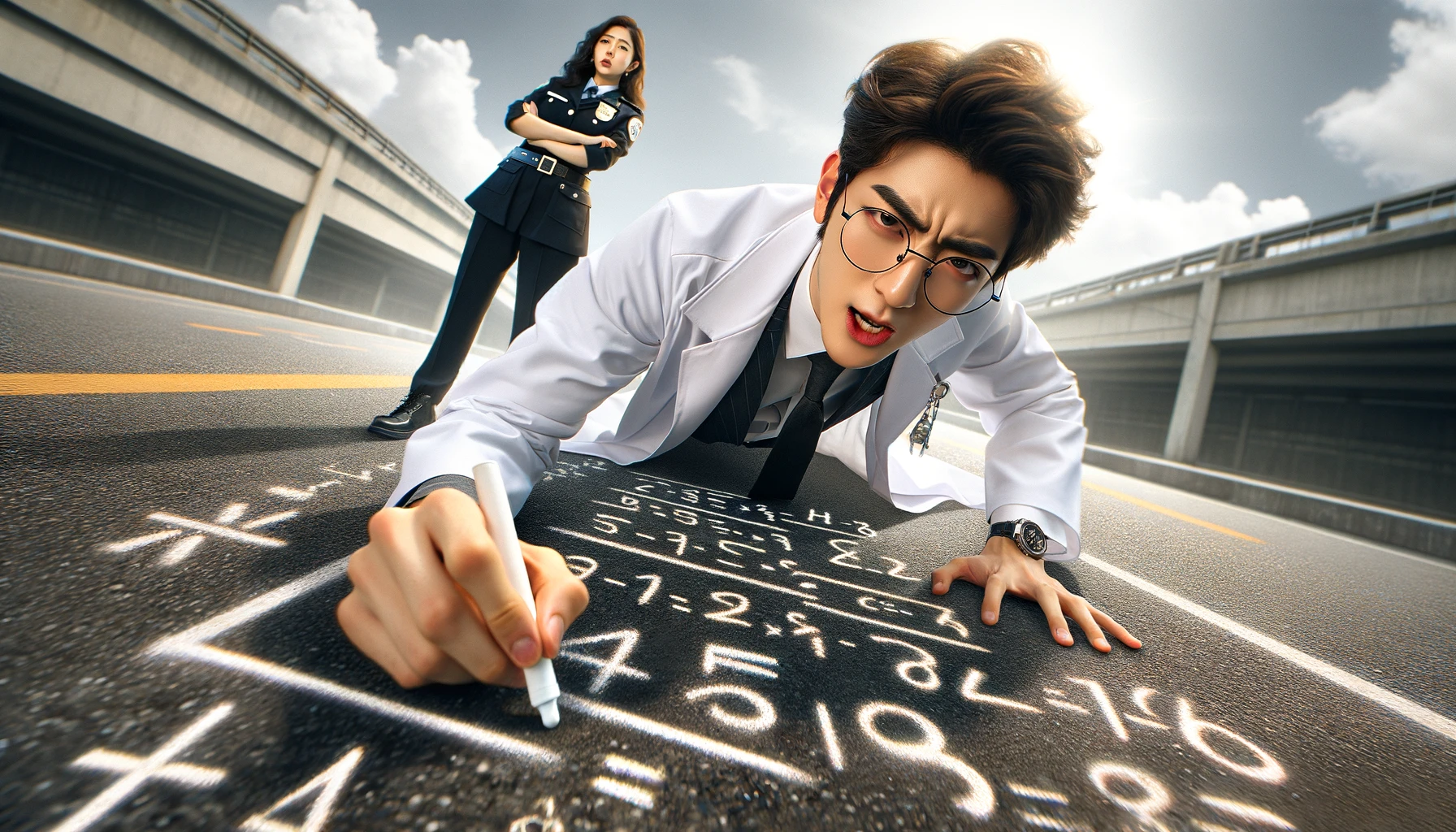
コメント