
こんにちは!データサイエンティストの青木和也(https://twitter.com/kaizen_oni)です!
今回の記事では、現代麻雀のバイブルとも言える「新 科学する麻雀」を読んで私が実践していることについて共有していきたいと思います。
本書はオンライン対戦麻雀「天鳳」の最高峰の卓「鳳凰卓」における約92万試合のデータを元に「相手の行動モデル」を再現するシミュレータを作成し、さまざまな状況下における打ち手の選択や収支を調査して1冊の書籍としてまとめた、まさに現代麻雀における聖典とも言える1冊になっています。
皆さんも本記事を読んで、麻雀において科学(=統計)を味方につけて戦うことの素晴らしさに気づいていただけると幸いです!
本書の概要
本書はオンライン対戦麻雀「天鳳」の最上位卓「鳳凰卓」の約92万試合の牌譜情報に基づいて「相手の行動モデル」を作成し、行動モデルを組み込んだシミュレータにあらゆる状況をインプットすることによって、「その場面においてどのような選択をする方が良い選択になる可能性が高いのか」を状況別に紹介してくれる、麻雀と統計好きの人間にはたまらない1冊となっています。
本書において、シミュレータを使って模索しているテーマは以下の22項目です
- 役ありメンゼンテンパイ、先制リーチすべきか
- テンパイ外しの判断
- シャボテンパイで先制リーチすべきか
- 先制メンゼンテンパイでの待ち選択
- 先制フリテンテンパイでの待ち選択
- 1軒リーチ下で追っかけリーチをすべきか
- 1軒リーチ下、副露テンパイから攻めるべきか
- 1軒リーチ下、メンゼン1シャンテンから攻めるべきか
- 1軒リーチ下、副露1シャンテンから攻めるべきか
- 2軒リーチ下、テンパイから攻めるべきか
- 2軒リーチ下、1シャンテンから攻めるべきか
- リーチ者の現物待ちでのメンゼン役ありテンパイ
- 1軒副露仕掛け下、テンパイから攻めるべきか
- 1軒副露仕掛け下、1シャンテンから攻めるべきか
- 2軒副露仕掛け下、テンパイから攻めるべきか
- 2軒副露仕掛け下、1シャンテンから攻めるべきか
- 染め仕掛け下、テンパイから攻めるべきか
- 染め仕掛け下、1シャンテンから攻めるべきか
- ドラポン仕掛け下、テンパイから攻めるべきか
- ドラポン仕掛け下、1シャンテンから攻めるべきか
- メンゼン1シャンテン、鳴いてテンパイすべきか
- その他の手組みに関する問題
上記リストを見るだけでも、「麻雀を科学的に解き明かそう」という著者の気合いの入りよう見て取れます。
私は本書の著者とつげき東北さんのことを麻雀を始めたての中学生の頃から師と崇めており、高校の頃にはとつげき東北さんのブログの内容を全て印刷し、麻雀を打つ際の指針として使っていたほどです。
当時からとつげき東北さんは天鳳の膨大なデータを元に、「どのような選択をするのが確率的に最も良いのか」を解説してくださるまさに現代麻雀の権化とも言えるお方でした。
前著「科学する麻雀」もそれは素晴らしい現代麻雀の教科書だったのですが、本書が今までのブログや前著「科学する麻雀」と大きく異なる点は、押し引き表にあります。
これこそ今回のシミュレータを使っているからこそなせる技であり、これによって
- 今何巡目か
- 待ちは良型か愚形か
- 何飜か
- リーチ時に初手切る牌はスジか、無筋か
- 追っかけ時の先制リーチ者は親か子か
などの多くの条件を加味した時に、それぞれの局収支の期待値がいくつであるかのシミュレーション結果を知ることができます。
これこそが今まで麻雀界に不足していた「ファクト」に他ならないのです。
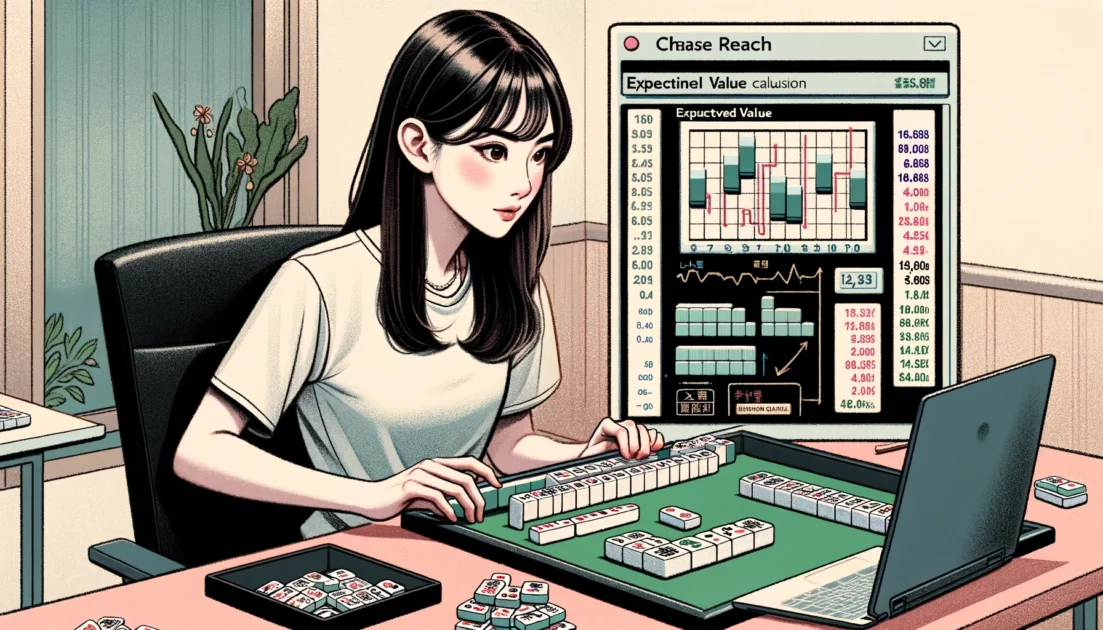
私が本書をどのように使っているか
私の打つ麻雀はこの「新 科学する麻雀」(とちょびっとの雀鬼流と少しの寿人流)に準拠しており、正しくこの本をバイブルとして使っています。
本書には押し引き表に基づいた多数の「ポイント」が掲載されています。
例えば以下のようなものです。
三面張、両面、字牌待ち、スジ待ちは巡目によらず即リーチが有利
とつげき東北『新科学する麻雀』(HOBBY JAPAN/2021) テーマ1 役ありメンゼンテンパイ、先制リーチすべきか P39
これらのポイントが全22テーマで複数ポイント紹介されており、とても一朝一夕に覚えて実践に使えるようになるわけではありません。
そのため、私は本書を麻雀を打つ日には必ず読み、その中でも「これは今までの僕の麻雀では使ってこなかったポイントだ」と思ったものは、そのポイントのルールをしっかり頭に叩き込み、その日の麻雀で実践するようにしています。
このような麻雀を科学した結果、期待値の観点からより勝ちやすい戦術を自分に少しずつ装備していくことによって、長い目で見たときに勝ちやすい人間になるように日々鍛錬をしているのです。
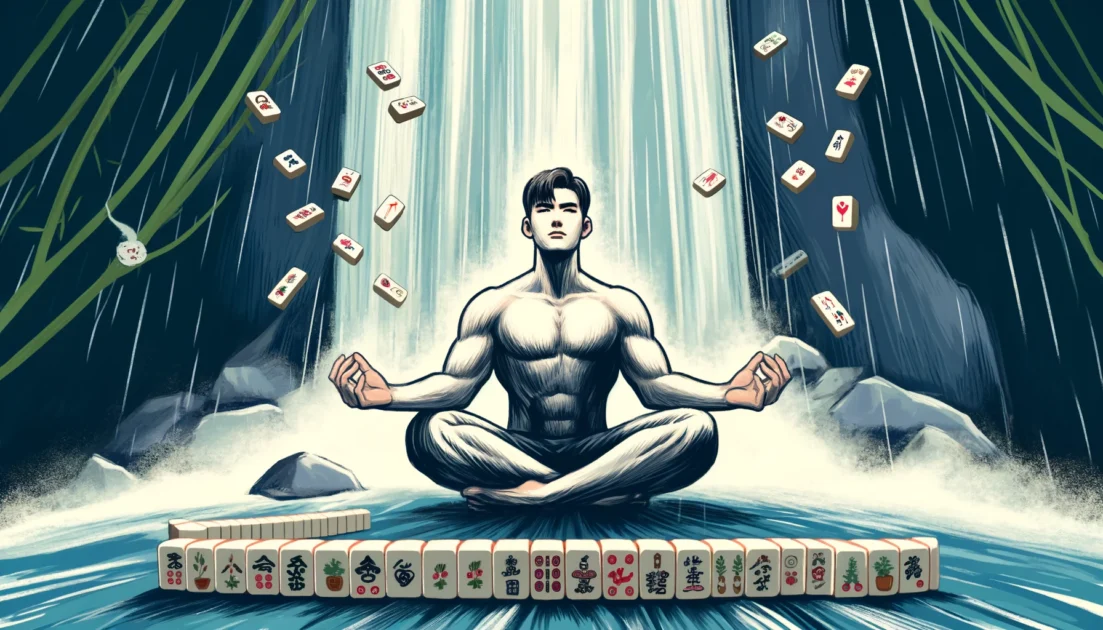
私が知って良かったと思っているTips3選
本書を読んで「そっちの方が期待値高かったのか!」と思わされたポイントは星の数ほどありますが、その中でも私の麻雀人生を大きく変えてくれたポイントを3つほど紹介しようと思います。
染め色の余り牌が出てきているかどうかがカギを握る
このポイントは「【テーマ18】染め仕掛け下、1シャンテンから攻めるべきか」における優先度Aのポイントです。
私は相手が副露で勝負をしてきている時の滅法弱いのですが、このポイントは私の染め手に対する防御力を底上げするとともに、染め手に対する攻撃力も一緒に上げてくれた有用すぎるポイントです。
ここで重要な点は「相手の染め手鳴き回数は何回か」「現在何巡目か」「相手の手から染め色がこぼれ落ちてきているか」です。
逆に言えば本書で明言しているように、2副露で余り牌が出てきていなければ全然押せるが、2副露で余り牌が出てくるといよいよ雲行きは怪しくなり、3副露で余り牌が出ているのはリーチを宣言されていることと同等なのです。
愚形テンパイでも2600点以上あるなら追っかけリーチが有利
これは「【テーマ6】1軒リーチ下で追っかけリーチすべきか」で出てくるポイントなのですが、このポイントは勝負に行くべきか行かざるべきか迷う僕の背中をそっと突き落としてくれる大事なポイントです。
特に一盃口や三色などの手替わりの選択肢も狭く、リーチをかけるか降りるかの選択を迫られた時には「統計的には攻めた方が期待値は高いのだから」と私に勇気をくれています。
対ドラポン1~2副露は対1軒リーチより押し寄り
これは「【テーマ20】ドラポン仕掛け下、1シャンテンから攻めるべきか」で出てくるポイントなのですが、これも何度も僕に勇気をくれました。
麻雀初心者の頃は誰かがドラポンをすると「満貫確定か、、、これは損失が大きいからオリだな、、、」とすごすご降りていたものですが、最近では「満貫が確定していたとしても、テンパイが確定とは限らないわけだから完全1シャンテンやリャンメンリャンメンで2飜もあれば期待値十分、あがれば相手の満貫はパーだ」と勝負に行くことができるようになりました。
これも自身のバイアスによる判断が、「科学する麻雀」によって矯正された良い例と言えます。
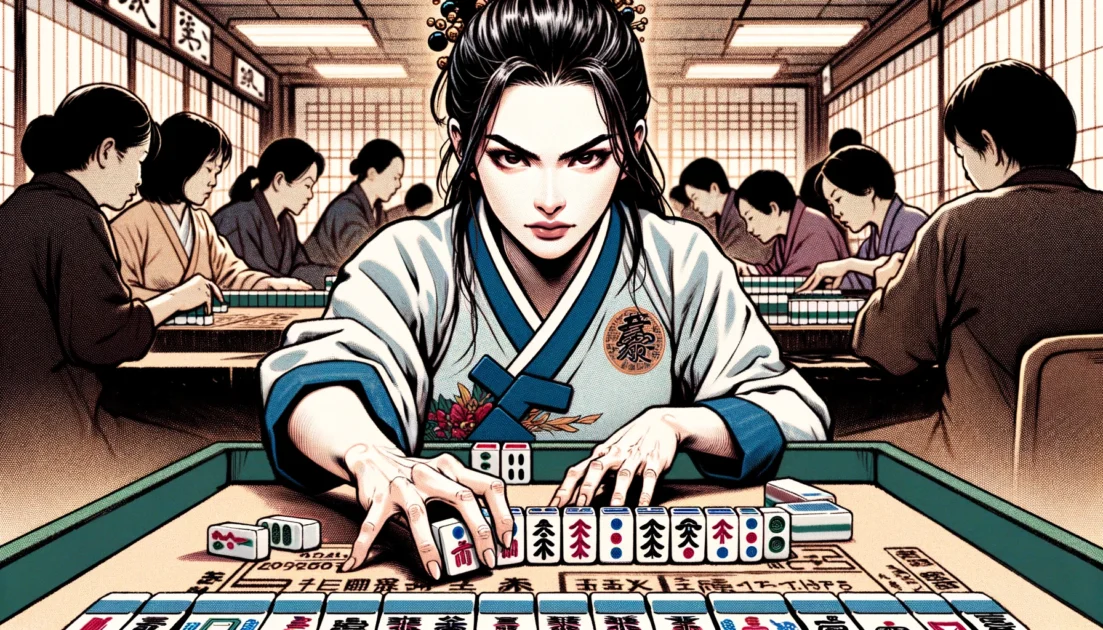
まとめ
今回の記事では、現代麻雀の、そして私のバイブルである「新 科学する麻雀」について、本書の概要を述べた後に、私なりの本書の使い方、本書で特に有用なポイント3選をご紹介いたしました。
デジタル麻雀を打つ方には必見の1冊ですし、特に「大事なところに限って間違った判断をしてしまうんだよな、、、」という方には麻雀を打つ際の羅針盤として、持っておくことをお勧めしたいです。
みなさんも麻雀を打ちに行く際には本書を小脇に抱えて、期待値の高い打ち手を少しずつ身につけながら麻雀ライフを楽しんでいただけると幸いです!
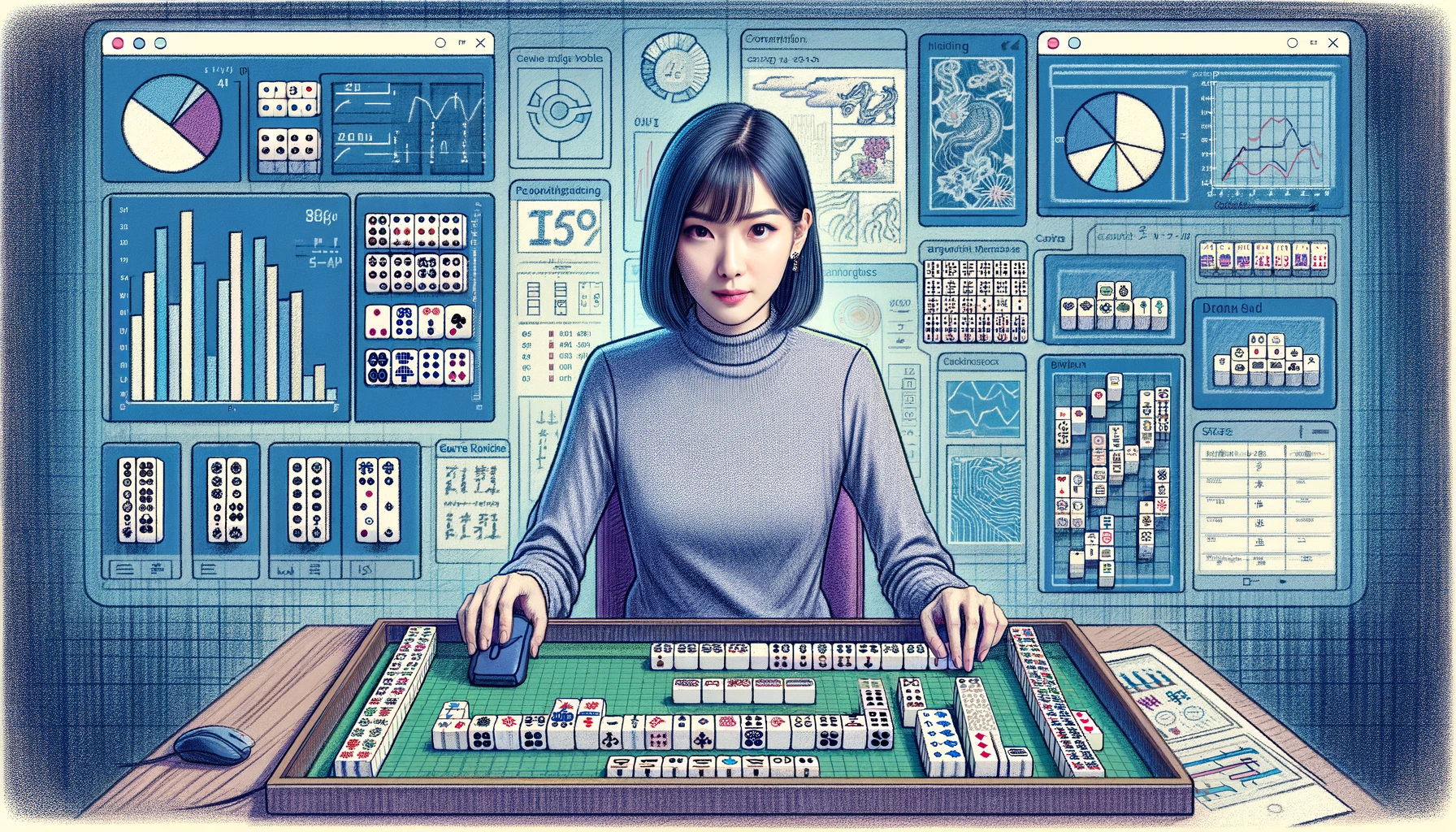
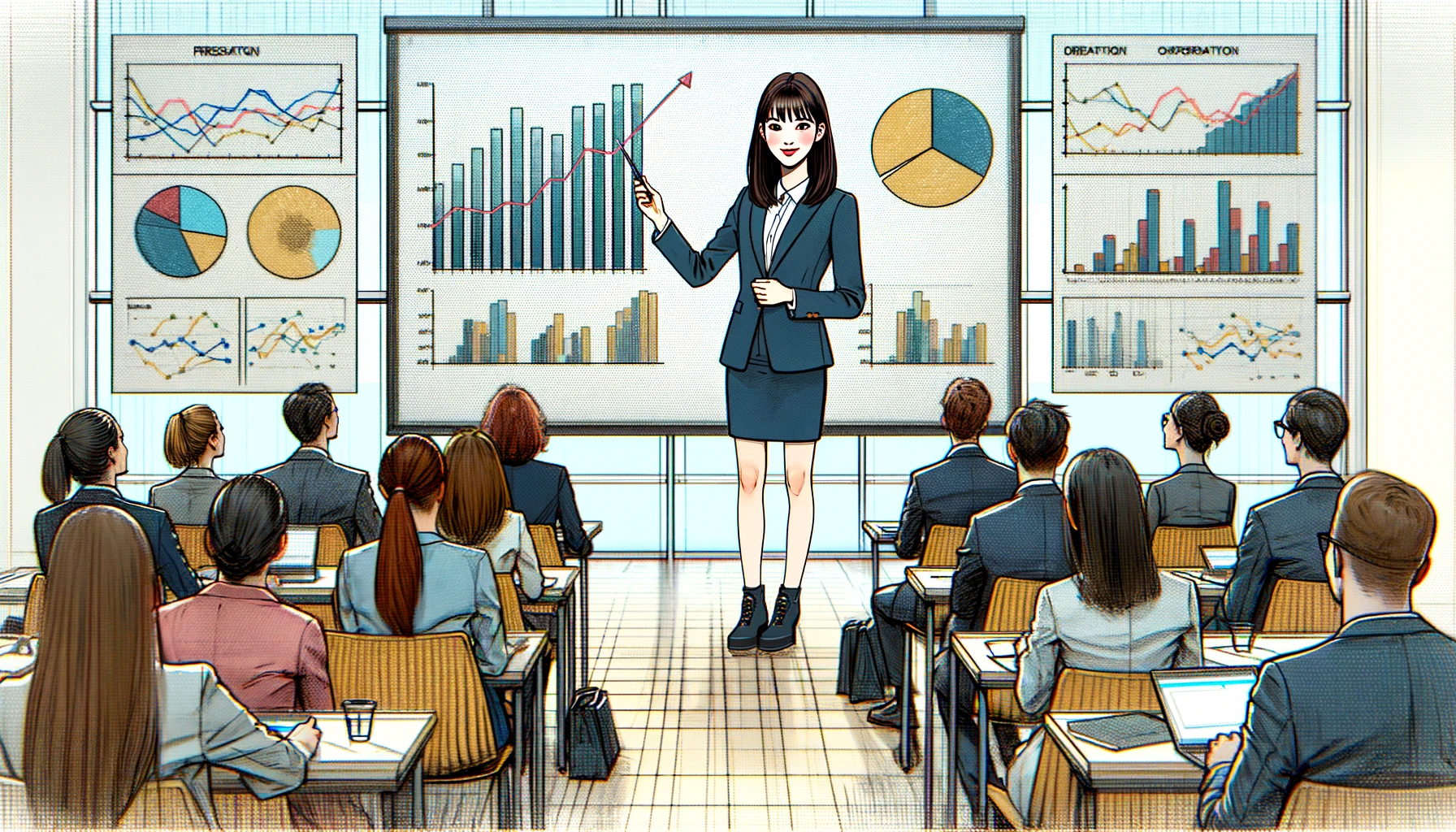

コメント