
こんにちは!データサイエンティストの青木和也(https://twitter.com/kaizen_oni)です!
仕事や人間関係で「同じことをぐるぐる考えてしまう」「いつまでも悩んで前に進めない」という経験、皆さんにはありませんか?
私自身も最近、自分では解いたことのない問題にぶち当たった時に「どうすればうまくいくのか?」を延々と考え続け、結果的に手が止まってしまう、またはとりあえず手をつけてみるものの上手くいかないことがよくある。
しかし最近、あるYouTube動画をきっかけに「悩み」が“時間の浪費”ではなく“思考の設計ミス”であることに気づきました。
その動画は『【ただのポジティブ思考じゃない】人間関係と仕事の悩みを一掃する最強の思考ロジック』と題され、悩まない人がどのようなステップで問題を処理しているかをチャート化した内容です。
本記事では、
- 私が動画を観る前に立てた仮説
- 実際に学んだ“多層的思考フロー”
- 具体的なワークフローとしての使い方
をまとめます。
「悩む時間をそぎ落とし、すぐに行動に移す」マインドセットを身につけたい方は、ぜひ最後までお読みください。
視聴前の仮説
動画を観る前に、私が考えた「悩みとの向き合い方」は次の3点でした。
- 悩むべきものと悩んでも仕方ないものを分ける
- 他人の評価や過去の失敗、雨が降っていること、など「自分でコントロールできないこと」は考えても無駄。
- 代わりに「何を変えられるか」「どう行動すればいいか」に意識をシフトすることが悩まない方法として語られているのではないか
- 悩むとは「解決できない問を繰り返す思考ループ」
- 同じ問いに延々と時間をかけてしまうのが悩みの本質。
- 悩まない人はそのループを早期に発見し、すぐ別の問いに切り替える仕組みを持っているのではないか
- 建設的な問いへの変換
- 雨が降るのを嘆くのではなく「傘をどう調達するか」「予定をどう組み直すか」を即座に問う。
- その問いへの答えを行動プランとしてストックし、悩む時間を限りなくゼロに近づけているのではないか
これらの仮説をもとに、動画の内容を“自分の思考プロセス”と照らし合わせながら検証します。
問題認識フェーズ:思い通りか、本当にうまくいっていないか
木下社長のお話で、悩まないために最初に重要なのは、目の前の問題を2段階で仕分けることです。
- 思い通りに行っていないだけか
- 例:目的地に電車で行こうとしたら運休→「思い通りに行っていない」だけ。
- 代替手段(バス、タクシー、徒歩、リモート会議など)を検討すれば、目的自体は達成可能。
- 本当に“うまくいっていない”のか
- そもそも目的(成果物の納品、良好な人間関係など)が絶対に達成不可能かを確認。
- 達成不可能なら次の「解消フェーズ」へ。
多くの“問題”は、実は手段の問題にすぎず、ここで感情的に落ち込む必要はありません。
「思い通り⇔うまくいかない」の判定を習慣化するだけで、悩みの大半は自動的に軽減されます。
「うまくいっていない」場合の3つの解消アプローチ
目的達成が難しいと判断した問題には、次の3パターンで対応します。
4-1. 原因解消思考(垂直的アプローチ)
- 定義:問題の“直接原因”を掘り下げ、既存の手法で取り除く。
- 例1:舗装の段差で荷物が破損→段差を補修する。
- 例2:システム障害で請求処理が止まった→障害ログを解析し、該当モジュールを修正。
経験や知見に基づき、原因→対策の縦方向にストレートに解決を図ります。
ただし「手を尽くしても外部要因に阻まれる」場合は、次のアプローチも併用します。
4-2. リフレーミング(問題を問題でなくする)
- 定義:問題の解釈を変え、「悩みそのもの」を消す心理技法。
- 例1:同僚の嫌味を「攻撃」と捉えるのではなく、「ストレス発散の表現」「環境要因の表れ」と解釈を転換。
- 例2:失敗を「能力不足」と感じるのではなく、「次に活かすための学び」とリフレーム。
問題を“外部事象+自分の解釈”に分解し、自分が抱くネガティブ感情を切り離すことで、
「問題=不快感」ではなく「問題=単なる出来事」に格下げできます。
4-3. 課題昇華(問題を具体的な課題に落とし込む)
- 定義:問題を「①考えれば解決」「②考えて無理でも、調べれば解決」「③考えても調べても解決不能」の3タイプに分類し、それぞれに応じた次の一手を設定する。
- ① 考えれば解決:自分の知識や経験で答えを導ける問題→徹底的に思考。
- ② 考えて無理でも、調べれば解決:情報収集や専門家への質問で答えが得られる問題→リサーチ計画を立てて実行。
- ③ 考えても調べても解決不能:そもそも未定義・不確実な未来→対処策の設計や受容、別選択肢の検討、そもそも対処しない・受け入れるという選択肢。
問題を漠然と放置せず、次々と「具体的課題」に昇華させることで、
悩む「だけ」の状態を脱し、必ず何らかのアウトプットに結びつけられます。
垂直思考 vs 水平思考の使い分け
上記アプローチをさらに強化する思考手法が2つあります。
5-1. 垂直思考(バーティカル)
- 特徴:原因→結果を直線的に掘り下げる。
- 例:ゴミ問題 → 「ゴミ箱を設置する」「回収ルートを作る」など、前提を変えずに対策。
5-2. 水平思考(ラテラル)
- 特徴:前提条件を疑い、別の切り口で課題解決を図る。
- 例1:食べられる容器を導入し、そもそも“ゴミ”自体をなくす。
- 例2:ゴミを店に持ち帰るとクーポンを配布 → ゴミが集客ツールに早変わり。
垂直思考で行き詰まったら、水平思考で前提を揺さぶり、斬新な解決策を生み出しましょう。
まとめ
本記事でご紹介した“最強思考ロジック”は、以下のステップを習慣化することが肝要です。
- 思い通り⇔うまくいかない を即判定
- 「うまくいかない」なら→①原因解消 ②リフレーミング ③課題昇華 で対応
- 垂直思考/水平思考を使い分け、既存解にこだわらず別解を模索
これらを実際に仕事や対人トラブルで試してみると、「悩む時間」が激減し、そのぶん「次の一手」に思考を集中できるようになるのでは、と思わされました。
私も今後問題発生時にはフローチャート的にこのアルゴリズムを回してみようと思います。
あなたの思考を一段深く設計するヒントになれば幸いです。


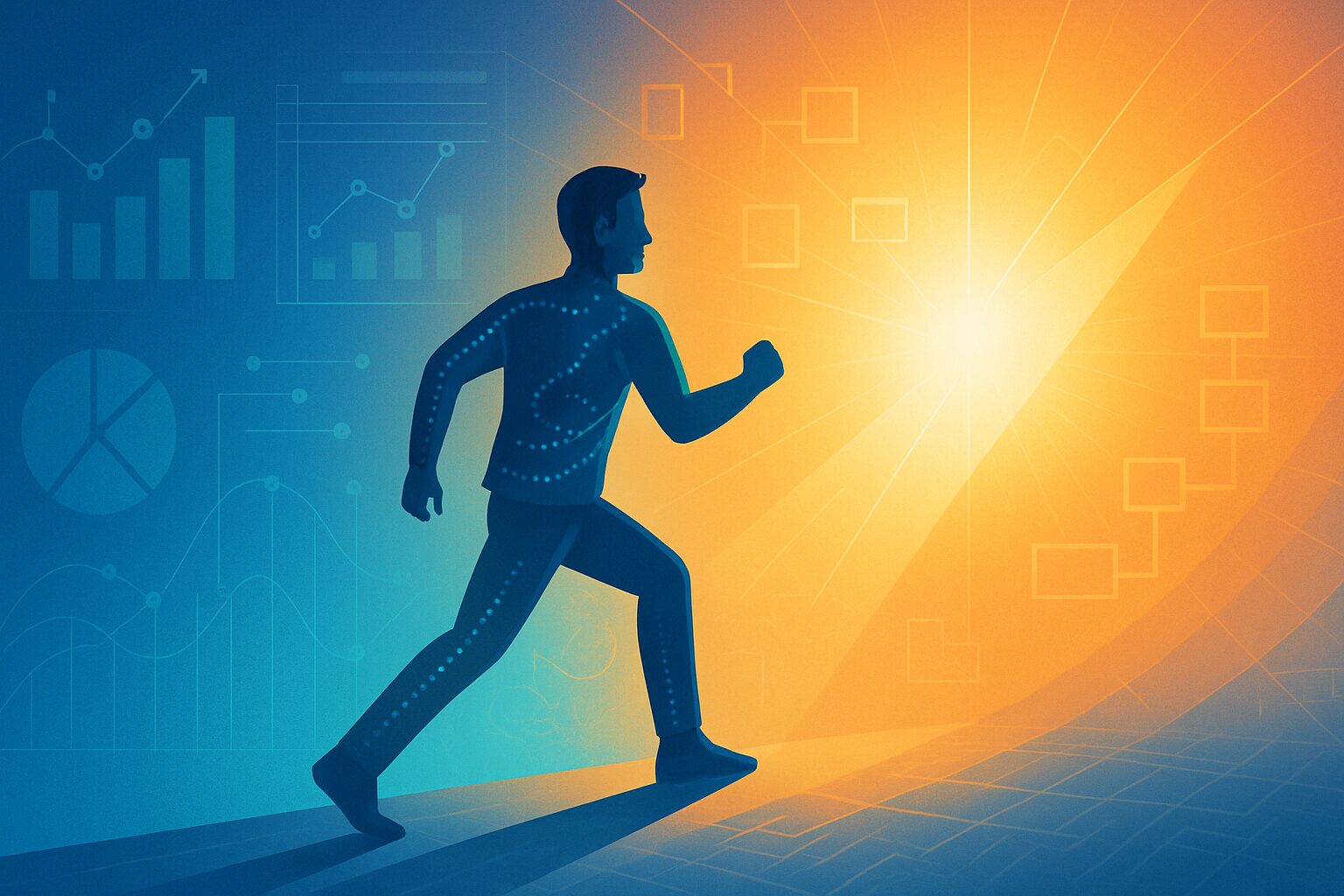
コメント