
こんにちは!データサイエンティストの青木和也(https://twitter.com/kaizen_oni)です!
今回の記事では、動画「【はじめる力】なにかを始めることは「スキル」なんです【前編】」という動画を視聴する前の仮説と視聴後の仮説を共有し、動画の視聴を通して実際に学んだことを共有したいと思います。
以前から「何かを始めること」は重要だと感じており、新しいことを始める、新しい場所に行くということはここ3年ほど継続して行なっているものの、「そもそもなぜ始めることが重要なのか」について深く考察をできていませんでした。
そこで本動画を通じて、“始める力”とは具体的に何を指し、どのように身につければいいのかをアップデートしたいと考えました。
視聴前の仮説
私は生成AIの登場により、アプリ開発や新規サービス立ち上げに必要なコストが大きく下がってきていると感じています。
学習コスト、初期開発コスト、そして情報収集コストが下がった今、差を生むのは「行動を起こす力」すなわち“始める力”ではないかと考えています。
ただ、私自身もまだアプリのリリースなどの以前からしたいと思っている行動を大きく起こせているわけではなく、そんな中でこの動画に触れ、安野さんが「始める力」をどのように捉えているのかを通じて、自分の思考をアップデートしたいと考えました。
本動画の構成としては、以下のように提示されています。
- なぜ今「はじめる力」が重要なのか
- 何かを始めるための3ステップ
- ステップ1:ゴールを見極める
- ステップ2:道筋を考える
- ステップ3:リスクを把握する
- リスクの形を知る
- リスクとの向き合い方
各セクションごとの仮説
1. なぜ今「はじめる力」が重要なのか
AIや生成系ツールにより、誰でもアイデアを形にしやすくなってきている。
その時に差を生むのは「まず始めてみる」力であり、行動しなければ機会損失が生まれる時代になったと考えています。
2. 始めるための3ステップ
- ゴールを見極める: 無目的に行動するのではなく、自分が何を達成したいのかを見定める力が重要。
- 道筋を考える: ビジョンに対してどのようなステップで到達するのか、その仮説を立てる。仮の戦略と初期のアクションプランを構築することが求められる。
- リスクを把握する: 行動によって起こりうる失敗やコスト(時間、金銭、信頼など)を認識しておく。特に大きなリスクがある場合は、行動を控えるべきかもしれない。
3. リスクの種類と向き合い方
- 人的リスク:信頼を失うリスク
- 金銭的リスク:大きな損失を被るリスク
- 時間的リスク:成果が出ずに時間を失うリスク
これらをどのように扱うかが「始める力」に深く関わる。
リスクを小さく分割できる場合、または一定の範囲内で受容できる場合はGO。
そうでなければ慎重にすべき。
以上が、動画視聴前の私の仮説です。
動画視聴後の学び(仮説の修正)
実際に動画を見て、私の仮説と比較しながら学びを整理しました。
なぜ今「はじめる力」が重要なのか ― 3つの視点
- 人生のコントロール性が上がる
行動を起こすことで、自分の意思で未来を切り拓ける自信が得られ、行動の選択肢が広がる - AIとの協働価値
AIは「始める」ことはできないからこそ、人が踏み出す一歩こそが、人間の価値を最大化する。 - 始めないこと自体が最大のリスク
不確実・変動の激しい時代には、「動かない」ことで機会損失や価値目減りを招く。
修正点: 「はじめないリスク」の具体例として投資の話が出され、インフレによってお金の価値が減少する状況においては行動しないことこそが最大のリスクであると述べられていました。
3ステップの深掘り
ステップ1:ゴールを見極める
- 発想のジャンプ力
ゴール設定は、論理的帰結ではなく「飛躍的なアイデア」で描く。
自分が“やりたい未来像”を大胆に掲げる力こそが重要。 - 論理的思考力
飛躍的ゴールを現実化するには、既存の知見や立証データを集めながら「なぜ」「どうやって」を詰める。 - 物語化能力
ゴールと道筋を他者に語れる形でストーリー化し、チームを巻き込む原動力にする。
魅力的な物語がなければ、ゴールが達成される可能性は低い。
修正点: 自分は当初「ゴール設定=少し先の目標」程度と捉えていましたが、動画では“個人の価値観・野心を反映した大胆なビジョン”を描くことが強調されていました。
ステップ2:道筋を考える(確率的思考)
- リスクの形を設計する
- 正規分布型:マイナスもプラスも平均回帰的に起きる -> あまり美味しくないリスクの形
- ポアソン型:マイナス側は限られるが、プラス側の可能性は無限大(宝くじ、印税収入)
- 逆ポアソン型:プラス側は限られるが、マイナス側の可能性は無限大(海外渡航保険)
- リスクにキャップをかける仕組み
- 借入(返済義務ありで正規分布型)ではなく、出資(マイナスはキャップありでプラス無限大)を活用
修正点: 自分は「リスクを洗い出し、許容上限を決める」レベルの仮説でしたが、動画では「リスク分布そのものを上手に設計し、キャップをかける仕組みを積極的に選ぶ」考え方に踏み込んでいました。
(次回予告)ステップ3:チームの組成
まとめ
- 始める力の価値は今、かつてないほど高まっている
AI時代・不確実性時代では、「動く者が勝つ」 - 仮説のアップデート
- 大胆なビジョン(発想の飛躍)こそが人の価値
- 論理+物語で筋道を設計
- リスク分布をデザインし、ポアソン型の期待値を狙い、圧倒的行動を図る
今回の動画を見て、自身の「新しいこと」にはビジョンや戦略が欠けているなと認識し直すことができたので、大志を抱いた上で間違っていてもいいので戦略を描いてみようと思います。
今回の記事が皆さんの「何かをはじめる」ことに少しで役立てましたら
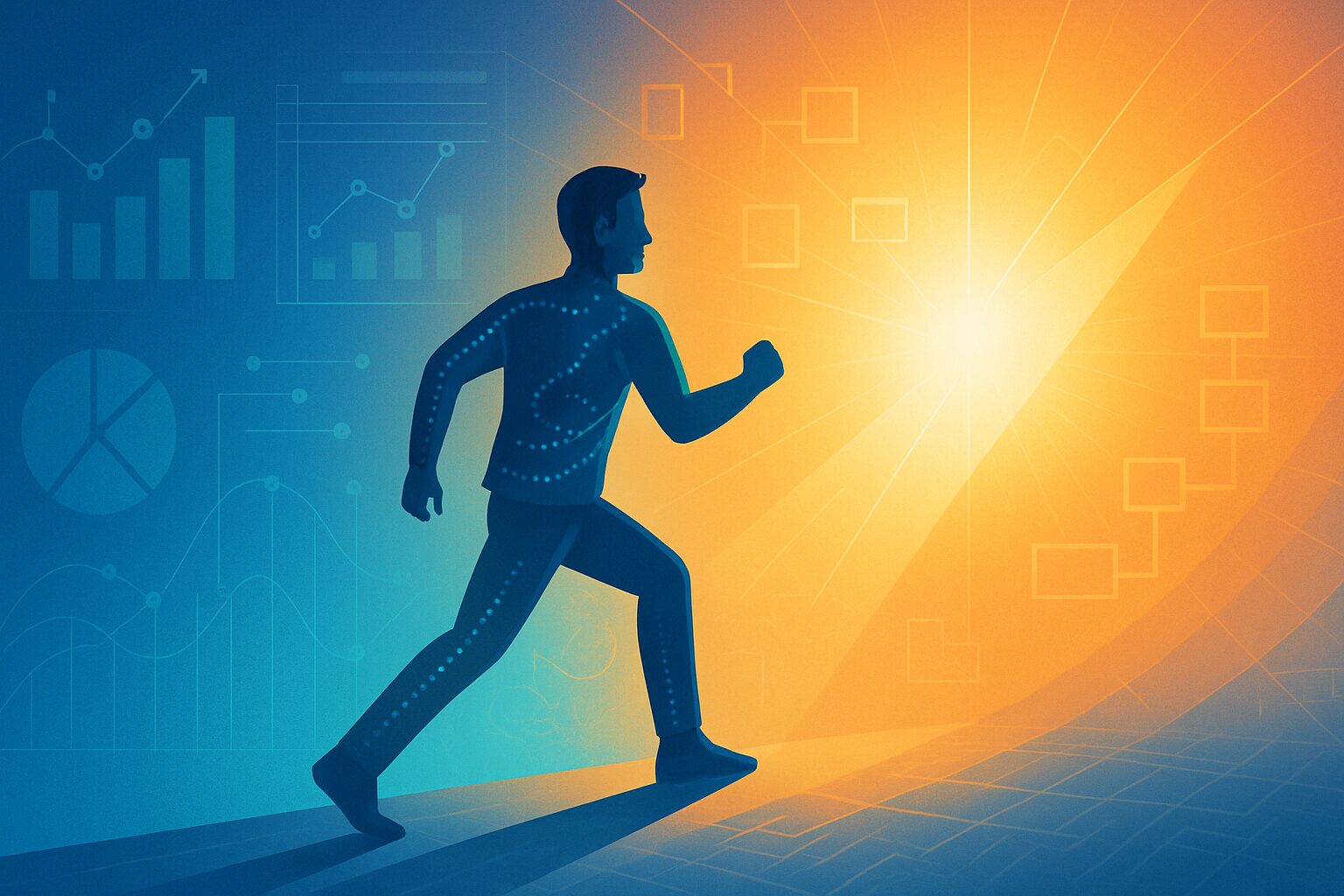

コメント